|
超音波検査(エコー) |
|
|
  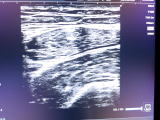  |
| 超音波検査(エコー)は産婦人科、心臓内科、消化器内科など、さまざまな分野で先駆して使われてきました。そういった流れから30年ほど遅れて整形外科分野でも少しずつ普及してきました。これまで十分に使われてこなかった理由として、浅部の解像度が今ひとつであったこと、読影が難しく何が写っているのか分からなかったことがあげられます。 整形外科での普及率は50%程度で、実際の使用はさらに少ない。普及しない最大の理由は、「難しくて読影できない。」に尽きます。ちょっと勉強したぐらいでは全く読めません。どのような画像診断であっても、まず正常像を頭に叩き込む必要があります。ところが、超音波の場合、いま映っているのが何なのかがはっきりしないのです。少しズレると教科書の画像とは大きく異なってしまいます。本はほとんどが静止画ですが、実際のエコーはリアルタイムで動く画像です。そのギャップが大きいのです。(最近では動画付きの専門書が出るようになってきました。) 加えて、整形外科では、およそあらゆる部位に対して体表からエコーを行いますので、頭に入れる正常像は星の数ほどあることになります。それゆえにいま一つ整形外科分野では普及しないのだと考えています。 しかしながら整形外科分野の診療を行う上では、エコーはとても有用なツールとなっています。レントゲンはそもそも骨の状態を知るものですし、軟部組織は写りますがそれほど情報はありません。エコーは骨の表面で跳ね返りますので骨の中の状態は分かりませんが、皮膚〜軟部組織〜骨の表面までは極めて情報量が豊富です。すなわち、外傷や疾病でレントゲンだけの診断を行うと骨以外の異常を見逃す可能性が高くなります。エコーだけでも骨の中の状況は分かりません。レントゲンとエコーを組み合わせると骨の中〜軟部組織〜皮膚まで全てが精査できることになります。 エコーが現れる30年前の整形外科では、レントゲンを撮影して「骨は大丈夫。」で済まされてきました。今の時代は骨折の有無に加え靭帯の損傷程度など軟部組織の状況をエコーで評価して治療に当たらないといけません。また、裂離(剥離)骨や小さな骨折はエコーでの描出の方がレントゲンより優れていることがあります。 例えば、肋骨骨折ではレントゲンでの診断率は50−60%でしかなく、エコーでは85%とされています。それ以外にもレントゲンで写ってこない骨折もエコーで発見できることもよくあります。また皮下腫瘍はエコーで診断できます。(もちろん確定診断は病理診断が必要です。)先日も、他院検診でガングリオンと診断された方はエコーでは神経鞘腫でした。ガングリオンは確率的には高いですけど、そう思い込まずにきちんと調べておくべきだと考えます。 触診で何でも分かるという「神の手」を持ってられる先生を除いて、一般の整形外科医ならやはり運動器のエコーは必須だと考えます。 |
| 2台目導入 超音波(エコー)検査はお手軽にいつでも出来ることも重要です。これまでの検査室に加えて診察室用に2台目を導入しました。まさしく聴診器代わりに超音波プローブをあてる時代となりました。 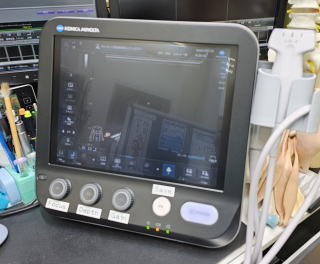 |
|
|