| 骨塩量測定DXA法 (二重エネルギーX線吸収測定法) 要予約・健康保険適応* |
| 予約TEL075-751-0616 |
| 健康診断の場合は、保険適応なし 1回5,000円 |
 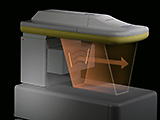 |
| 骨粗しょう症の治療もお任せください |
| ・年間骨粗しょう症診断・治療実績186名(令和6年6月末現在) ・骨粗しょう症の治療に豊富な経験を持っています。 年間で186名以上の方々に骨粗しょう症の診断と治療を提供しております(令和6年6月末現在)。 骨の量は16歳から18歳で最も多く、50歳を過ぎると少しずつ減っていきます。 この減少をどのように防ぐか、また骨が折れてしまった場合の対応はどうすべきかなど幅広く対応します。 ・骨粗しょう症学会の診療ガイドラインや最新の研究結果に基づいた治療を行っています。 また、他の医療機関で骨粗しょう症の治療を受けてられる方もお気楽に検査の相談をしてください。 薬の選択や治療方針など、治療が適切かどうか、いつでもご相談いただけます。 ・骨粗しょう症による圧迫骨折や脆弱性骨折にも対応しています。 骨粗しょう症の症状は、骨が折れるまで現れないことがあります。 また、骨が少しずつ折れていくと、気づかないこともあります。 何かの拍子に急に痛みが出たり、身長が縮んだりすることもあります。 これらを予防するためには、骨塩量が減らないうちに日々の生活習慣や食事、運動などを見直すことが大切です。 ・骨塩量の変化を追うためには、腰椎や大腿骨のDXA検査が最も有効です。 手のDXAやその他の骨塩量測定方法では、正確さに欠けることがあります。 |
|
|
|
骨粗しょう症の検査(骨密度測定 腰椎・大腿骨DXA法) |
|
|
| 2017年4月1日より腰椎・大腿骨DXA法(日立DCS-900F)による骨量測定(骨塩定量・骨密度測定)を開始しました。これは最も正確な測定法として、日本骨粗鬆症学会、日本骨代謝学会、骨粗鬆症財団が作成した「骨粗鬆症の予防とガイドライン2015」で推奨されている方式です。 これまでも手の中手骨や橈骨で行われてきましたが、必ずし全身の骨塩量を反映しておらず、腰椎や大腿骨での測定がより正確で骨粗鬆症の把握に優れているとしています。 実際、運用を開始して腰椎、大腿骨で測定すると手での骨塩量と大きく異なることもあり、新たに骨粗しょう症の治療が必要なこ ともありました。また逆に骨粗しょう症と診断され治療を受けてきたが、腰椎・大腿骨DXAでは正常であったケースもあります。さらに治療経過中の骨塩量の変化は腰椎・大腿骨DXAでないと正確性に欠けるとされています。 |
  寝ているだけで測定できます。腰椎、大腿骨それぞれ40秒です。 |
|
|
| 骨粗鬆症の概要 |
|
|
骨粗しょう症は骨に含まれる骨塩(主にカルシウム)が減少し、骨がスカスカになる病気です。症状は進行して骨折が起こるまでは殆どありません。骨折が起こると痛みが生じますが、それもまた軽いものから強いものまで幅があります。知らぬ間に「いつの間にか骨折」が起こっていることもよくあります。痛みが無く、徐々に身長が低くなるときは要注意です。骨粗しょう症が進行すると、脆弱性骨折といって、ごく弱い力が加わっても骨折が起こります。骨折がよく起こる部位としては、脊椎(胸椎、腰椎)、骨盤、大腿骨頸部、手関節、肋骨です。身体を支える脊椎、骨盤、大腿骨に骨折が起こると、痛みのために歩行が困難となり、放っておくと寝たきりにつながります。 <骨粗しょう症の診断> 骨密度がYAM(若年成人平均)の70%以下の場合(原則として腰椎または大腿骨近位部骨密度とす 脊椎圧迫骨折または大腿骨頚部骨折の脆弱性骨折がある場合 それ以外(手関節、肋骨など)の脆弱性骨折があり、 (骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2015年版) |
|
|
| いつの間にか骨折を予防しましょう |
|
|
|
骨粗しょう症は、「骨密度」と「骨質」が低下し、骨がもろくなることで骨折しやすくなる病気です。現在、全国で約1,280万人が骨粗しょう症と推定されており、特に女性に多く、年々患者数は増加傾向にあります。 原因としては、加齢やホルモンの変化、過度の飲酒・喫煙、ビタミン不足、ステロイドなどのお薬の影響などが挙げられます。原因を見極め、早期に診断・治療を行うことが大切です。 骨粗しょう症に伴う骨折のリスクは高く、年間約15万人が大腿骨近位部を骨折しているとされています。さらに背骨の骨折(椎体骨折)は、70代女性で約5人に1人が経験すると報告されています。こうした骨折は移動能力や日常生活の質の低下を招き、死亡率を高める可能性もあります。 診断は、診察・画像検査・血液検査・骨密度測定などを組み合わせて行います。当院では、精度の高い骨密度測定装置を導入しており、1回の受診で診断を完了することも可能です。 骨密度検査が推奨されるのは、65歳以上の女性、70歳以上の男性、既に骨折を経験された方、大腿骨近位部骨折の家族歴がある方などです。検査の必要性は総合的に判断いたしますので、ご希望の方はお気軽にご相談ください。 治療については、原因に応じた対応を行います。骨量が低下している場合は、内服薬や注射薬を用いた治療を開始します。これらのお薬は骨折リスクを3〜5割程度低下させることが期待されています。当院では、症状や生活スタイルに応じて、継続しやすい治療法をご提案しています。 栄養面では、カルシウム、ビタミンD・Kの摂取が重要です。小魚、乳製品、魚介類、納豆、緑黄色野菜などを適度に取り入れることが予防につながります。 また、運動も大切です。ウォーキングやストレッチ、水中運動などが骨やバランス能力の維持に効果的とされています。当院では、個々の体力に合わせた筋力トレーニングやリハビリプログラムのご案内も行っております。 骨粗しょう症は身近な病気ですが、適切な診断と治療により予防や改善が可能です。気になることがありましたら、どうぞいつでもご相談ください。当院では、皆さまの健康を守るための情報発信にも力を入れてまいります。 |
|
|